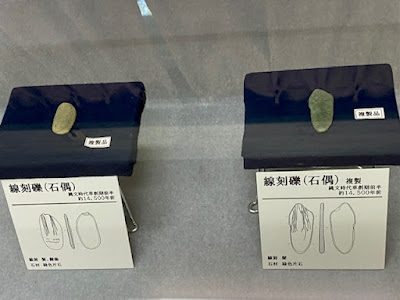公開日2023/04/06
[晴れ時々ちょっと横道]第103回 愛媛大学大学院 地域レジリエンス学環 誕生!
 |
| 愛媛大学大学院 地域レジリエンス学環のパンフレットです。 |
令和5年4月1日、国立大学法人愛媛大学に新しい大学院修士課程コースが誕生しました。その名も『地域レジリエンス学環』。この地域レジリエンス学環は文部科学省が法令で定める「研究科等連係課程制度」を活用して、愛媛大学の人文社会科学研究科、教育学研究科、医学系研究科、理工学研究科、農学研究科という既存の5つの研究科(大学院修士課程コース)すべてが、理系、文系の学部の枠を超えて連携することで設置されるもので、既存の学問分野を横断的、複合的に学び、実践的能力を身に付けるための教育を行うことを目的としています。この「研究科等連係課程制度」を活用した大学院修士課程コース、愛媛大学では令和4年4月に設置された「医農融合公衆衛生学環」に続き2つ目となりますが、文系、理系といった従来の枠組みを超えた連携は、初めてのことになります。
https://www.rr.ehime-u.ac.jp 愛媛大学地域レジリエンス学環HP
 |
| 愛媛大学の城北キャンパスです。地域レジリエンス学環はこの城北キャンパスだけでなく、地域協働インターンシップでは西条(西条市)、南予(西予市)、中予(東温市)の愛媛大学地域協働センターも学びのフィールドにします。 |
“レジリエンス(resilience)”とは“強靭性”や“復元力”のこと。愛媛県を含む四国地域は、近年の地球温暖化により頻発化する豪雨や周期的に動く南海トラフによる大地震といった自然災害リスクに曝されています。また、少子・高齢化が全国で最も早く進んでいる地域の一つであり、社会活動の中断を迫られるような大きな変化の中でも、柔軟かつしなやかな対応ができ持続可能性のある地域社会づくりが喫緊の課題になっています。この課題に対応していくためには、災害に強い強靭な社会基盤整備を進めていくだけではなく、人と自然、人と社会との繋がりを通して、地域の基軸産業である農業や漁業、林業といった第一次産業や観光といった地場の産業を活性化させ、誰もが住みがいのある地域を築くために、地域のこれまで、そしてこれからを展望し、事前に策を打っていける人材の育成というものが強く求められています。地域レジリエンス学環は、このような状況を踏まえて、愛媛県という地域が抱える様々な課題を解決する人材を、従来の大学教育の枠組みを超えて養成していくことを目的として、愛媛大学に設けられた新しい形の大学院修士課程コースです。言ってみれば、「愛媛県独自の地域のためのビジネススクール」とでも言えばいいのでしょうか。このような総合大学のすべての研究科・学部が文系理系といった従来の研究科・学部の垣根を超えて連携し、地域課題解決に向けた人材を養成する大学院が設置されるのは、おそらく愛媛大学が全国でも初めてのことではないでしょうか。素晴らしい取り組みだと私は思います。
で、不肖私 越智正昭、この愛媛大学の新しい大学院修士課程コース「地域レジリエンス学環」発足と同時に、そこの客員教授に就任させていただきました。今や年間売上2兆円を超える巨大企業NTTデータの事業部長、さらには本社営業企画部長という経営幹部として同社グループ全体の営業改革を主導した経験に加えて、気象情報会社ハレックスという年間売上10億円規模の中小企業(ベンチャー企業)の代表取締役社長を15年間務め、同社を単なる気象情報の提供会社から気象ビッグデータを活用したソリューション提供企業へと変革し、経営を再建させることを主導したDX(Digital Transformation)の実践者というほぼ両極端とも言える経歴が買われたもののようです。
私は愛媛大学では昨年度から主に法文学部や社会共創学部の学生を対象に「文系学生のためのデータサイエンス入門」という愛媛県寄附講座のプロデューサー兼非常勤講師を務めさせていただいておりましたが、それに加えて、昨年夏に行われた工学部の土木工学関連の先生方を対象とした勉強会で愛媛デジタルデータソリューション協会(EDS)の会長としてDX(Digital Transformation)に関する講演をさせていただいた際、当時、防災工学の立場から地域レジリエンス学環設置準備室で中心的役割を果たされておられたM教授の目に止まり、M教授からアプローチをいただいたのがきっかけでした。防災だけでなく、地域経済の基軸をなす農業や漁業といった産業の活性化には気象に関する情報の活用は不可欠なものであり、気象情報会社の代表取締役社長を15年間も務めさせていただき、今も気象庁が事務局を務める気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)の副座長を務めさせていただいている経歴も、愛媛大学にはたいへん魅力的に映ったのでしょう。その後、地域レジリエンス学環の講義内容や運営形態等に関して幾つかの相談に乗りアドバイスをさせていただき、その目的と方向性に大いに賛同させていただいたことから、昨年末に私の客員教授就任と、組織としての愛媛デジタルデータソリューション協会(EDS)との連携の打診をいただきました。もちろん、どちらも二つ返事で快諾させていただきました。
発足と同時の就任ですので、愛媛大学地域レジリエンス学環としては学外から招く最初の客員教授ということになります。客員教授として、私は学生さん達のメンター(Mentor)の役割を期待されているようです。地域レジリエンス学環の初年度の学生8人のうち5人は社会人学生。その社会人学生の方々はまさに多士済々。年齢も様々で、地元企業の経営幹部をはじめ、実に多彩な業種業態の様々なお立場の方々が含まれていて、共通するのは地元愛媛を特に経済面からなんとかしたいという強い思い。そういう方々の相談に乗ったり助言をすることは、申し訳ないですがビジネス経験の少ない正規の大学の先生方にはいささか難しく、その部分を民間企業の経営経験のある私が補うって形です。また、学環のテーマである防災や農業・漁業、観光などの地域経済の分野では気象や地象が大きく絡むことから、その方面でのアドバイザーとしての役割も期待されているようです。
また、地域レジリエンス学環では、実践科目としてプロジェクト形式による地域協働インターンシップや、地域をフィールドにした協働力や実践力を涵養することを目的とした地域レジリエンスPBL(Project Based Learning:課題解決型学習)が必須科目として設けられていて、学生が自ら問題・課題を見つけ、さらにその問題・課題を自ら解決する能力を身に付けることを重要視しています。この地域レジリエンスPBLにおいては、地域理解や分野横断的な専門学識だけでなく、ICT(情報通信・処理技術)やデータ利活用力が大きく求められてきます。このICTやデータ利活用力の分野では、私が会長を務めさせていただいている愛媛デジタルデータソリューション協会(EDS)が“連携組織”として文部科学省提出資料の中にも愛媛県デジタル戦略室とともに正式に位置づけられていて、お手伝いをさせていただくことになっています。
さらに、私は今年度も愛媛大学、松山大学、松山東雲女子大学・同短期大学、聖カタリナ大学、人間環境大学という愛媛県内6つの大学でデジタル人材育成のための愛媛県寄附講座の全体プロデューサーと非常勤講師を務めさせていただくことになっているのですが、そのデジタル人材育成に関する愛媛県寄附講座で教えていることの柱はデザイン思考。様々な課題の深層究明、そしてその課題に対する解決策を立案するための考え方、アプローチの仕方を教えるということで、地域課題を解決できる人材を養成するという愛媛大学地域レジリエンス学環の目指す方向性とピタリ一致します。すなわち、愛媛大学地域レジリエンス学環は県内6つの大学で現在行なっているデジタル人材育成の上位に位置付けされるものと言うこともでき、大学院修士課程コースだけに、愛媛大学だけでなく県内の他の大学でデジタル人材育成の講義を受講する学生さん達にとっても、もっと高度なことを学ぶための進学先の有力な選択肢の一つになり得るということを意味します。その意味でも、私が地域レジリエンス学環の客員教授に就任することの意義は大きいと思っています
昨年の12月19日に愛媛県と愛媛大学、松山大学、松山東雲女子大学、人間環境大学という県内の4つの大学がデジタル人材育成に関して覚書を締結し、連携を進めていくことになりました。その連携覚書の中では、「地域の課題を解決できる人材の輩出」や「教員や学生の人的交流や施設の相互利用」など6つの項目での連携が盛り込まれており、この愛媛大学地域レジリエンス学環という大学院修士課程コースの開設は、その一環としても捉えることができると認識しています。よく“産官学連携”という言葉を聞きますが、この愛媛大学地域レジリエンス学環や、県内6大学におけるデジタル人材育成に関する愛媛県寄附講座においては、私が絡む以上、理想的な“産官学連携”の実現を目指していきたいと考えています。愛媛大学は前々から社会連携の推進に積極的に取り組んでいる大学ですし。
ということで、自分で言うのもなんですが、私が愛媛大学地域レジリエンス学環の客員教授に就任することの意義、期待されていることは、私が思っている以上に大きいようで、その期待の大きさにプレッシャーを感じながらも、これまで誰もやってこなかったことだけに、大きなやり甲斐も感じているところです。
また、前述のように、地域レジリエンス学環は愛媛大学の人文社会科学研究科、教育学研究科、医学系研究科、理工学研究科、農学研究科という既存の5つの研究科(大学院修士課程コース)の連携により運営されるもので、教授陣もそれらの研究科から選ばれた28人もの正規の教授・准教授の先生方が揃っています。そういうそれぞれの分野の専門家である錚々たる先生がたと連携して、郷里愛媛県が抱える課題解決のための意見交換や議論ができるのがメチャメチャ楽しみです。客員とは言っても、そういう先生がたと“同僚”になるわけですからね。
私は現在67歳。愛媛大学地域レジリエンス学環の客員教授は、おそらく私のキャリアでは最後に名乗ることになるであろう役職名(肩書き)ではないか…と思っています。私はこれまで、課長代理、課長、部長、統括部長、事業部長、営業企画部長、そして社長、顧問…等々、様々な役職名で呼ばれてきましたが、この愛媛大学地域レジリエンス学環客員教授が今は自分に一番しっくりくる役職名のような感じがしています。郷里松山の大先輩で日露戦争の英雄、そして司馬遼太郎先生の名作『坂の上の雲』の主人公の1人である秋山好古陸軍大将は私の憧れの人物で、私は秋山好古陸軍大将の名言「男子は生涯 一事を成せば足る」を座右の銘にして、その一事をずっと追い求めていたようなところがあったのですが、その一事をやっと見つけられた感じ…とでも言ったほうがいいでしょうか。私のこれまでの様々な経験は、この愛媛大学地域レジリエンス学環の客員教授として地域課題を解決する人材を養成する仕組み作りに参画するためにあったのではないか…と。年齢的に言っても私がこの先自分1人の力でできることは極めて限られていますが、自分のこれまでの経験で得た知識や考え方を次の世代を担う多くの若い人達に伝え、その成長を後押しさせていただくことで、世の中により大きな足跡を残すことができそうだ…ということで、今は大きなワクワク感を感じています。郷里愛媛県の発展のため、人材育成の面で、もうしばらく貢献をさせていただきます。もしかすると、秋山好古陸軍大将にとっての“一事”とは、日露戦争における沙河会戦、黒溝台会戦、奉天会戦などで、騎兵戦術を駆使して当時世界最強と呼ばれたロシアのコサック騎兵師団を破るという奇跡を起こして日本軍の勝利をもたらしたことよりも、晩年、故郷松山の人達に請われて私立北予中学校(現在の県立松山北高校)の校長を務めたことのほうだったのかもしれません。秋山好古陸軍大将が北予中学校の校長に就任したのが65歳の時。今の私とさして変わりません。
このように、愛媛県内のデジタル化は、まずは人材育成の仕組みづくりの面から、他の都道府県に先駆け大きく歩み出そうとしています。郷里愛媛県をデジタル先進県にするという大きな野望の実現に向けて、また一歩前進です。ウンウン、愛媛の未来は明るい!!
【追記】
地域レジリエンス学環の設立目的は、デジタルデータを活用して地域の課題を解決できる人材を養成するということで、そのために文系、理系といった従来の枠組みを超えて学内すべての5研究科、7学部の連携による大学院修士課程コースを設置するということなので、これはもう大学という教育機関における立派なDX(digital transformation)と呼んでもいいことだと、私は思います。大学が自らDXを実践したうえで、学生達にDXについて教える……この愛媛大学の取り組みは大変に素晴らしいことだと思います。そもそも自らDX、特に“変革”を主体的に経験してきた人以外には、DXを次の社会を担う学生達に教える資格はない!…くらいに私は思っています。いくら本で読んだだけの小難しい知識や理論、技法等を語っても、学生達の心にはちっとも響きませんから。その意味で、この愛媛大学の地域レジリエンス学環の開設は、全国の大学における今後のデジタル人材育成に、大きなインパクトを与えることになるかもしれません。